{{ items[0].title }}
中央大学附属高校は当時は男子校で、体育館で入学式を行なっていた。
満員電車が嫌いなために、自宅から一番近い高等学校というのでそこに進むことにしたが、高校生になったら、中学時代に少し始めていた(エレキベース、キーボード)バンドを本格的にやるか、演劇部に入ろうと思っていた。
入学式の冒頭、まだ名前も知らない同級生と整列して開式を待っていると、いきなり、2階のバルコニーからカッコイイファンファーレに始まる有名な?曲が聞こえてきた。後で分かったことだがそのカッコイイ楽器はホルンである。
その曲は、その頃「伊豆エメラルドタウン」という分譲地のコマーシャルに使われていたもので、ヘリコプターで緑の大地が撮影されると山本直純先生の指揮姿が映って、「いずエメラルド〜タウン〜」と、自然に合唱につながるというシロモノであったので、生来(今でも)知ったかぶりの国から知ったかぶりを広めにきた人間である僕は、(緑の森の画像の印象から)反射的に「お!『田園交響曲』やってるじゃん!」と、僕の前に立っていたこれから同級生になる男に教えてやった。その男は振り返って「こいつ、すごいこと知ってるな〜」という驚きの目で僕を見たので、ちょっと鼻が高かった。
しばらく演奏した後、アナウンスが入り「ただいまの演奏は、吹奏楽部の皆さんによる交響曲「新世界」でした」ということだ。
その男はギョッとした感じでこちらを振り向いたが、「〜〜♪」という感じで、目を合わせないようにしながら冷や汗をかいていた。「くっそー、分譲地だから『田園』かと思ったぜ・・・新開発だから『新世界』か〜〜。くっそ〜、甘かった・・・・」と、どっちの曲もよく知らないくせに知ったかぶった自分を棚に上げて悔しがっていた。

それにしても、中学校までは生徒の合奏といえばせいぜいがリコーダー30人とか、ピアニカとかにカスタ+トライアングル+大太鼓など打楽器が加わるような「ぷー、ぷー、ちか、ちか、どん、しゃん、ぷー!」という「教育楽器+ドナウ河のさざなみ」のレベルだったのが、いきなり、プロが使っているような楽器で交響曲とかを演奏する高校生って神?と驚いたのは間違いなかった。
この話はそれで終わる(終わらせたい)予定だったのだが、入学式が終わって校舎内を歩いていたら、さっきその楽器(ホルン)をかっこよく吹いていたツカダ先輩が、廊下でまたその楽器、そのメロディを吹いていた。(今にして思えば、それは「新世界」の中でも第4楽章の冒頭のところであった。)吸い寄せられるように、近くでその楽器を見てみたいということもあってふらふらと近寄っていくと、あっという間に部室に一名様ご案内〜〜、気づいた時にはクラリネットを咥えさせられ、「あ!音が出た!普通半年かかるのに!!経験者?天才?」とか全国的に有名な悪魔の誘惑をかまされて、「うちの高校、軽音も演劇部もないから!」という残念な情報までいただき、その日のうちに吹奏楽部に入部(クラリネット)が決定していたのであった。(もちろん、未経験)僻地の国語教師を目指していた穏やかな人生が狂った瞬間だった。

入部すると、部屋に入っていく時などの挨拶が大きな声で「ちわ!」であること、遅刻すると正座、などの決まりごとを習い、平日は朝バルコニーで校歌を演奏、放課後は教室に丸く並べた椅子でクラリネット・パートの怖い先輩たちとボーボーと練習し、土曜日が「合奏」という毎日が始まった。パートリーダーはのちにサクソフォンに転向されて今もアマチュアで現役の野村先輩という方。ノナカ・ミュージックハウスにもよく来てると思いますのでサイン貰ってください。このクラブ活動では珍しい「自分の楽器持ち」なほどの音楽好きで、非常に知識豊富で面白い方でした。
その頃「テーエン」(定期演奏会)に向けて練習していたのは
*エルザ
*春の声
*未完成
という、なんと言いますか、今にして思えばドイツロマン派重大作曲家の「クラシック音楽特集であった。「エルザ」の優雅な弦楽器の序奏部分はバリトン・サックス初心者などの爆発的音響によりやや妨げられていたとはいえ、中学校の授業で「タンホイザー行進曲」を歌って以来のワグナー通(本人評価)だった自分には嬉しい選曲で、ことに最初の方にある美しいオーボエ・ソロには毎回胸ときめいたものだった。
*ああ、一応書いとくと、
ワグナー:楽劇「ローエングリン」第2幕より「エルザの大聖堂への入場」が正しい題名。

これを演奏しておられたのは、中大附属高校ブラス始まって2代目のオーボエ奏者の長田(おさだ)先輩で、このかたは非常に優しい、ちょっと女の子のような清潔な感じの方で、(男子校内の誇大錯覚現象含む)今自分が手にしているクラリネットよりもはるかに細身の楽器、リードから発せされる繊細なオーボエの音にとてもマッチしたお方であった。

そして!
クラリネットのパート練習で3連符とかが演奏できなくて廊下をマラソンさせられたりしていると、この長田先輩はたった一人で静かに練習しておられる。
クラリネットは多分8人くらいいましたが、オーボエは一名だけだったから当然だ。ここに目をつけたのが、そもそも団体行動とか運動とか目上の人とかが大嫌いな茂木少年であったことは言うまでもない。「オーボエになれば・・・・一人で練習すればいいのか・・・」と、悪魔の誘惑は少年の人生をいよいよ狂わせようとするのであった。
ちなみに、「未完成」の冒頭、あの密やかな弦楽器の16分音符の伴奏は、8人のクラリネット、バス・クラリネット、数人のサクソフォンなどによってぼがぼがぼがぼごぼご、ほがほがほがほがほがほが、と動物園の食事時間のように変身していた(原曲を聴いたことがなかったので、一体これはなんなのだろう?と、心底不思議に思いながら初心者茂木少年もまたぼぼぼぼぼぼ、と、サードクラ(3rd.Cl.)パートの、できない低音域のタンギングで唾液まみれになりつつも演奏しておった。特に第2楽章のオーボエ・ソロは大変長く、かつ美しいもので、あれ吹いてみてーなー!と思いつつもボーボー言っておった。しかしこのクラブ活動の決まりは、「自分の担当じゃない楽器吹いちゃダメ!」というのを含んでおり、遊びでバリサクとか「ペット」とかトロンボーンを吹いては叱られていた(今でも指遣いとかポジションなんとなく知っており、指揮者として大変便利です。笑)から、先輩の個人楽器であるオーボエは絶対触れなかった。
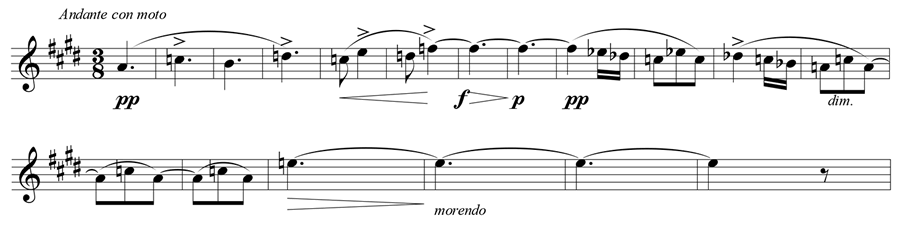
しかし、そのソロはなんと、その後、本当に吹くことができた、と言うのは、その後オケマンになったから、と言うのではなく、(それはもう>原曲:a-mollでたくさん吹きました。)中大附属高校吹奏楽部のうん10周年記念「テー演」と言うものが50歳くらいの時にあり、そこでこの未完成のソロを一緒に吹かせていただいた、と言うことであった。実はこの段階では、もはや100回以上オケで吹いていて、徹底的に指遣いやブレス、音程のポイントなどを叩き込んでしまった後であり、なんとそれよりも半音上(だったかな?珍しく。半音下ではなかった。)のB♭-mollに編曲されたそのソロは、異常とも言える難しさになっておった。
演奏前に会場アナウンスで、「本日の特別ゲスト:NHKコーキョー楽団首席オーボエ奏者の、茂木大輔先輩です!」と女子アナ(すでにこの段階で共学。)に紹介されて演奏が始まったが、多分3回くらいミスったと思います。いやもう恥ずかしい。
と言うわけで、「クラ」に居ながらにしてエルザに始まり未完成につながるオーボエへの憧れ、この武蔵小金井のポンコツなクラブ活動(「部活」とは呼ばなかった。)には大変な指導者がお二人と、もっと本当に大変なOBが来てくれていたのが、このトリオで茂木大輔少年の人生を、先々までさらに深く狂わせていくのだが、そのお話はまた次回。(続く)
追伸:長田先輩の使っていた楽器は、とても珍しいイギリス式(親指板:サム・プレート・システム)のオーボエで、後年、不要になったと言うのでお譲りいただき今も保管している。これが俺の人生を狂わせたのか、くぬ、くぬ〜〜!と、時々痛めつけるためである。興味ある方にはお目にかけます。
次回の更新は、2023年10月を予定しています。
お楽しみに。